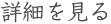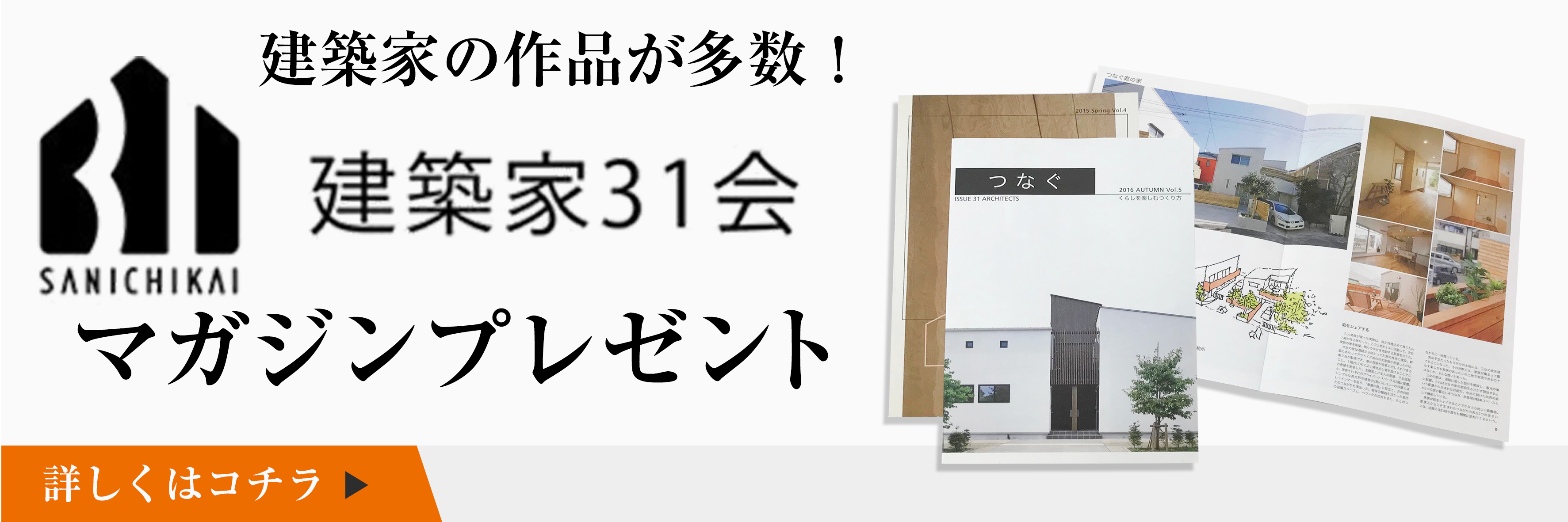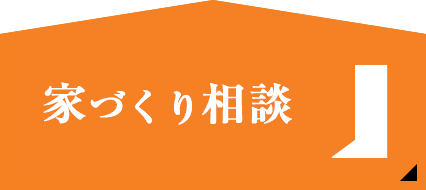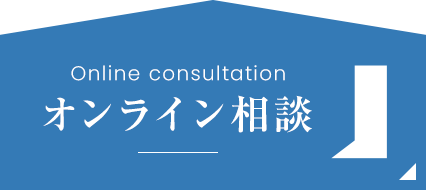「竣工後のお付き合い 」@角倉剛
ザハ・ハディッド氏の新国立競技場の当選案において、建設に向けた手続きが進む中で、その工事費と共に問題とされたのが、完成後の多額の維持費です。
建築は出来上がってからの付き合いが長くなるということを、回収の見込みが立たない維持費に憂鬱になりながら、改めて思うことになりました。
先日、以前設計監理をした個人住宅のお施主さんが、竣工後10年の節目をお祝いするイベントを開催されるというので、私も参加してきました。「家縛りプロジェクト」というアーチスト松本春菜さんの活動なのですが、アーテストと参加者で家を紅白の荒縄で縦横十時に縛り、10歳を迎えた住宅のお祝いをしてきました。
この住宅は、個人事務所を構えて最初の頃に設計した住宅です。10年たっても祝福される住宅の姿は、建築が長く使われるということ、竣工後も設計者としてお付き合いが続くということの喜びを教えてくれました。
10年建つと建物も、いろんな不具合がおきることがあります。この住宅でもお祝いのご招待を受ける少し前に雨漏りの連絡を受け、施工者と共に、対応をしてきたところでした。問題は、防水シートの継ぎ目の自然劣化ということで、幸いなことに防水の保証期間内であったため、無償での対応をしてもらうことができました。こんな少し嫌なことが起きた後に受けたご招待でしたので、竣工してからも続く信頼関係をありがたく思いました。
竣工後の住宅の中には、残念なことが起きたものもあります。とにかく安く造ってくれと言う話が先行してしまい、値段重視で選んだ工務店は、1人の現場監督がいくつもの現場を掛け持ちすることで、経費を削減している工務店でした。結果として、現場監督の目が行き届かなかったのでしょう、竣工後には、施工不良が原因となったトラブルがいくつか起きてしまいました。挙げ句の果てにその工務店は倒産してしまい、その後の対応を別工務店にお願いすることになってしまいました。やはり可能であれば、造った工務店にできるだけ面倒を見てもらいたかっただけに残念です。
冒頭に触れた新国立競技場への自らの対案を提示して、問題点を指摘された槇文彦さんの著書「漂うモダニズム」(左右社)の中で、建築に対する評価のあり方について、下記の様に述べられています。
「(建築に対する)メディアによくある時評なるものを私は好まない。なぜなら建築は人間と同じく長く生命を維持していくものであり、その全貌は生まれたての子供からは分からないからである」
生まれたての子供が育っていく(建築の場合は厳密には経年劣化のみだが)過程を支えていくことも、私たち設計事務所と工務店の役割であり、その長く維持される建築の生命の間、お施主さんとの付き合いは続きます。
「住宅を作るということは、親戚が増えるようなものだ」と例える建築家もいます。相性も含め、その長きに渡るパートナーシップを築くことができるどうかの見極めも、家造りの依頼先を考える上で、重要な指標のひとつであることを、最近起きた出来事のいくつかから感じています。
− 最新イベント情報 −
2月28日(土)住まいの「なかみ」構造見学会のお知らせ @小泉拓也+栗原守
どんなふうにできあがっていくのか、どうやってつくられているのか…住まいの“なかみ”とは、出来上がった時には隠れてしまうところ。見る機会の少ない工事途中を見ていただくものです。 無垢の柱や梁などの構造材、Baubioとセルロースファイバーの断熱材、通気の工夫などの“なかみ”を実際に見ていただきながら詳しく説明をします。光設計の「呼吸する住まい」の“なかみ”を見ることができるいい機会ですので、是非ご参加ください。 会場:杉並区荻窪 「スロープ玄関の小さな木の家」 ...