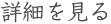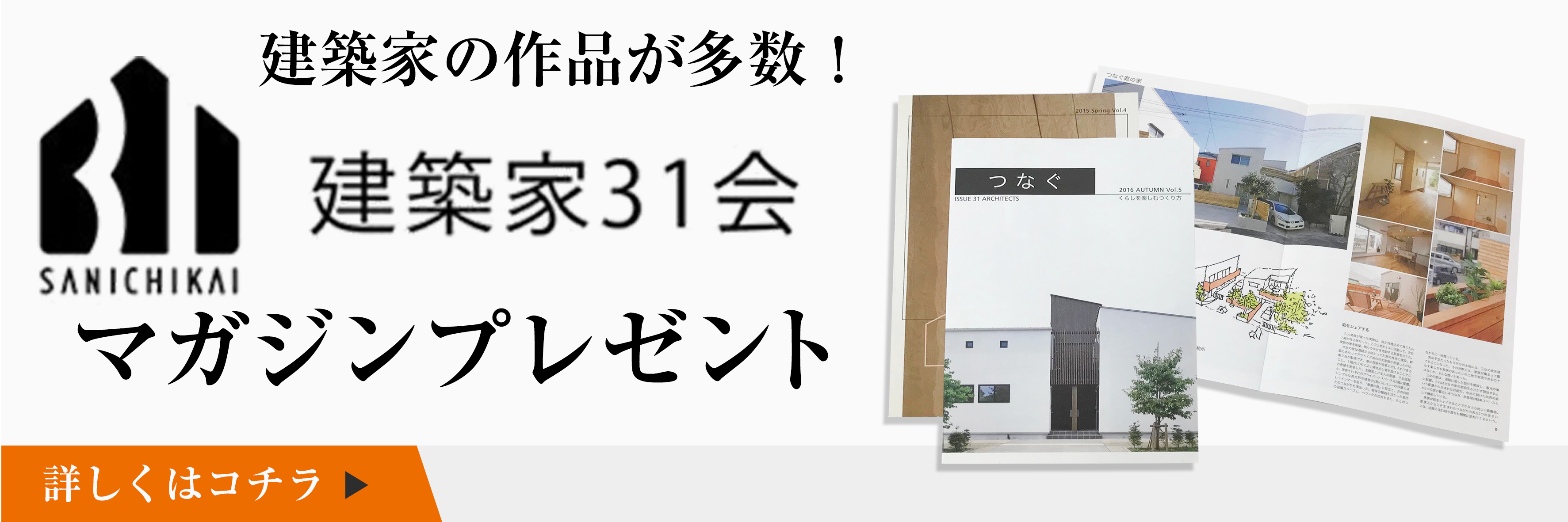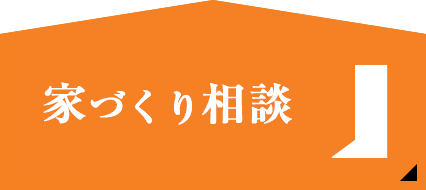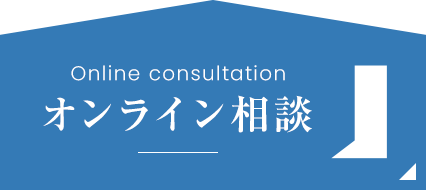マンションリフォームで広間茶室をつくる数寄屋大工さん
今週のリレーブログ担当、ギルドデザインの磯村です。
年初の担当となり、年初の挨拶で、吉岡徳仁のガラスの茶室の写真を使わせていただきましたつながりで、今週は、昨年当社が設計監理し、マンションリフォームをして造った茶室の話をしたいと思います。
茶室といわれても、一般の方には少し縁遠く、敷居が高い存在、よくわからないものかもしれませんが、狭い和室というイメージはありませんか?
この計画は、茶道の先生が、生徒さんにお稽古をしてもらうための茶室の計画です。一通りのお稽古がつけられる広さとなると、8畳の広間の茶室となります。

綺麗に仕上がった和室、茶室ですが、そこには職人さんたちの丁寧な仕事の積み重ねがあります。
少し難しいかもしれませんが、仕上がれば隠れてしまう部分、綺麗に見せる、狂いがこないようにするための細工など、大工さんの仕事を紹介します。
この現場では、エレベーターや階段で2間(約3.6m)の長さ材料が運べなかったため、8畳の長さで必要な2間の長さの造作材(敷居、鴨居、天井材など)が、すべて繋ぎとなってしまいました。


敷居(左)と欄間鴨居(右)の接合部分です。金物を使ってきっちりと締め込んで繋いでいます。
木材は乾燥していくうちに、ねじれたり、隙ができるものですが、空調が行き届いた現代の住宅では、尚更です。
柱と鴨居、柱と敷居などの接合部分の仕口には、大変な手間をかけて加工しています。とりわけ、数寄屋と呼ばれる丸太を扱うような造作では、自然の曲線を意識しての加工が必要です。




左上は、鴨居の仕口加工の様子で、右上が仕上がった鴨居を、上から見たところです。
最近、住宅工事の大工さんは、鑿を使うところを見たことがありませんが、数寄屋造りの大工さん達では、当たり前の道具です。
左下が、鴨居と柱の取付いた状態です。乾燥収縮による隙が出ないように、仕口の加工に加えて、金物でもしっかりと締め込んでおきます。
右下は、敷居と柱の取り付きの様子です。柱の欠き込みの中にある穴は、敷居をボルトで締めこむためのものです。
詳しい現場の様子などはこちらからどうぞ。
「マンションの茶席」ブログ
ギルドデザインHPはこちら
![]()
− 最新イベント情報 −
2月28日(土)住まいの「なかみ」構造見学会のお知らせ @小泉拓也+栗原守
どんなふうにできあがっていくのか、どうやってつくられているのか…住まいの“なかみ”とは、出来上がった時には隠れてしまうところ。見る機会の少ない工事途中を見ていただくものです。 無垢の柱や梁などの構造材、Baubioとセルロースファイバーの断熱材、通気の工夫などの“なかみ”を実際に見ていただきながら詳しく説明をします。光設計の「呼吸する住まい」の“なかみ”を見ることができるいい機会ですので、是非ご参加ください。 会場:杉並区荻窪 「スロープ玄関の小さな木の家」 ...