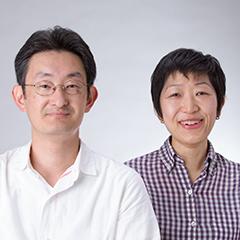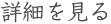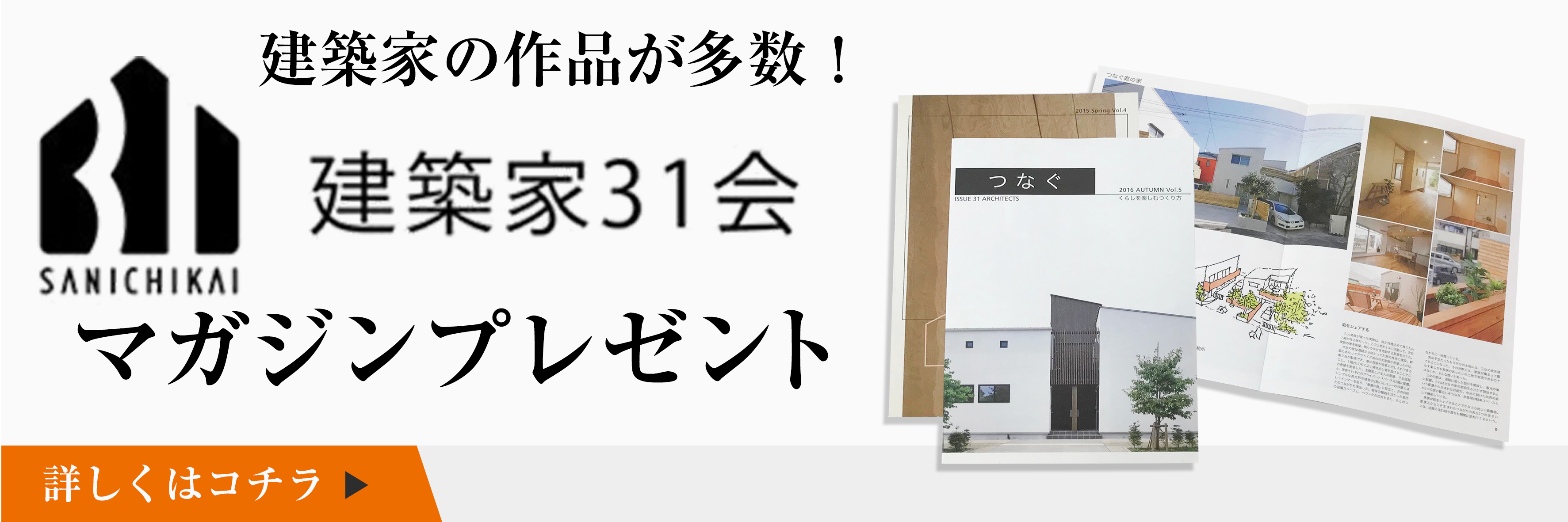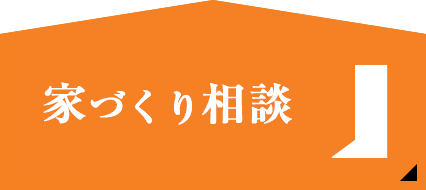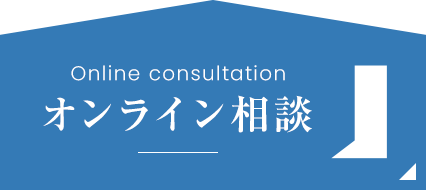音楽室のある家をつくる-4@菰田真志+菰田晶
今週のリレーブログ担当の菰田(こもだ)建築設計事務所の菰田真志です。
昨日に引き続き音楽室に関して書こうと思います。
今日は部屋形状による音の調整/縦横高さの黄金比の仕様についてです。
音楽室を設計するにあたって音を出したときにどういった響きをするのかということが重要になります。一部分に音がまわらなかったり、残響が不自然に長かったり短かったりすると気持ちよく音を楽しむことができなくなります。
音の調整はある程度仕上材や音響装置でも調整可能ですが、根本的な部屋の大きさや形が考えられていないと後での調整が出来ないこともありますので、部屋形状はよく考えておく必要があります。
基本は平行面を作らないことが重要です。向かい合う壁が並行になることで起こるフラッターエコーが起こらないように壁に角度をつけることが非常に有効です。壁だけではなく、床と天井といった面に関しても同じです。平面計画上壁に角度を付けられない場合には壁の仕上面をジグザクにしたり、反射板を取り付けたりと言ったことで対処することもできます。
直方体の部屋(反射板等を使わない素の状態)で考える場合には、縦横高さの黄金比というものがあります。部屋全体に音が廻ったときに一部分に音が集中したり聞こえない部分がでたりといった音響障害の出にくい部屋の縦横高さの比を言い、「2:3:5」や「1:1.7:2.9」といった比率が言われています。
本格的な試聴室や音楽ホール、スタジオなどでは、遮音壁で囲われた内部に音響調整のための壁を更に立てて、その壁の間で反射や吸音といった音響調整をすることもあるのですが、なかなかそこまでの音響設計をすることは費用の面でも難しいので、基本の部屋形状でできることをしっかりしておくことが重要です。
天井高の高い空間のほうが演奏者の弾いているときの気持ちがよいといわれます。天井高を高くした場合に吹抜に面してロフトやギャラリーを設けることもできますが、極端に奥行きが違ったり、張り出している客席のような形状だと別の響きが重なったり、張り出しの下は音が悪かったりすることがあるので、そういった部分も注意が必要です。
後日書こうと思っていますが、残響時間は部屋の体積・表面積にも関係しますので、残響時間との兼ね合いも含めて計画しましょう。
明日は使用する室内仕上材/吸音・反射・拡散の調整について書いてみたいと思います。
よろしくおねがいいたします。
(有)菰田建築設計事務所 菰田真志
http://www.archi-komo.co.jp/
− 最新イベント情報 −
2月28日(土)住まいの「なかみ」構造見学会のお知らせ @小泉拓也+栗原守
どんなふうにできあがっていくのか、どうやってつくられているのか…住まいの“なかみ”とは、出来上がった時には隠れてしまうところ。見る機会の少ない工事途中を見ていただくものです。 無垢の柱や梁などの構造材、Baubioとセルロースファイバーの断熱材、通気の工夫などの“なかみ”を実際に見ていただきながら詳しく説明をします。光設計の「呼吸する住まい」の“なかみ”を見ることができるいい機会ですので、是非ご参加ください。 会場:杉並区荻窪 「スロープ玄関の小さな木の家」 ...