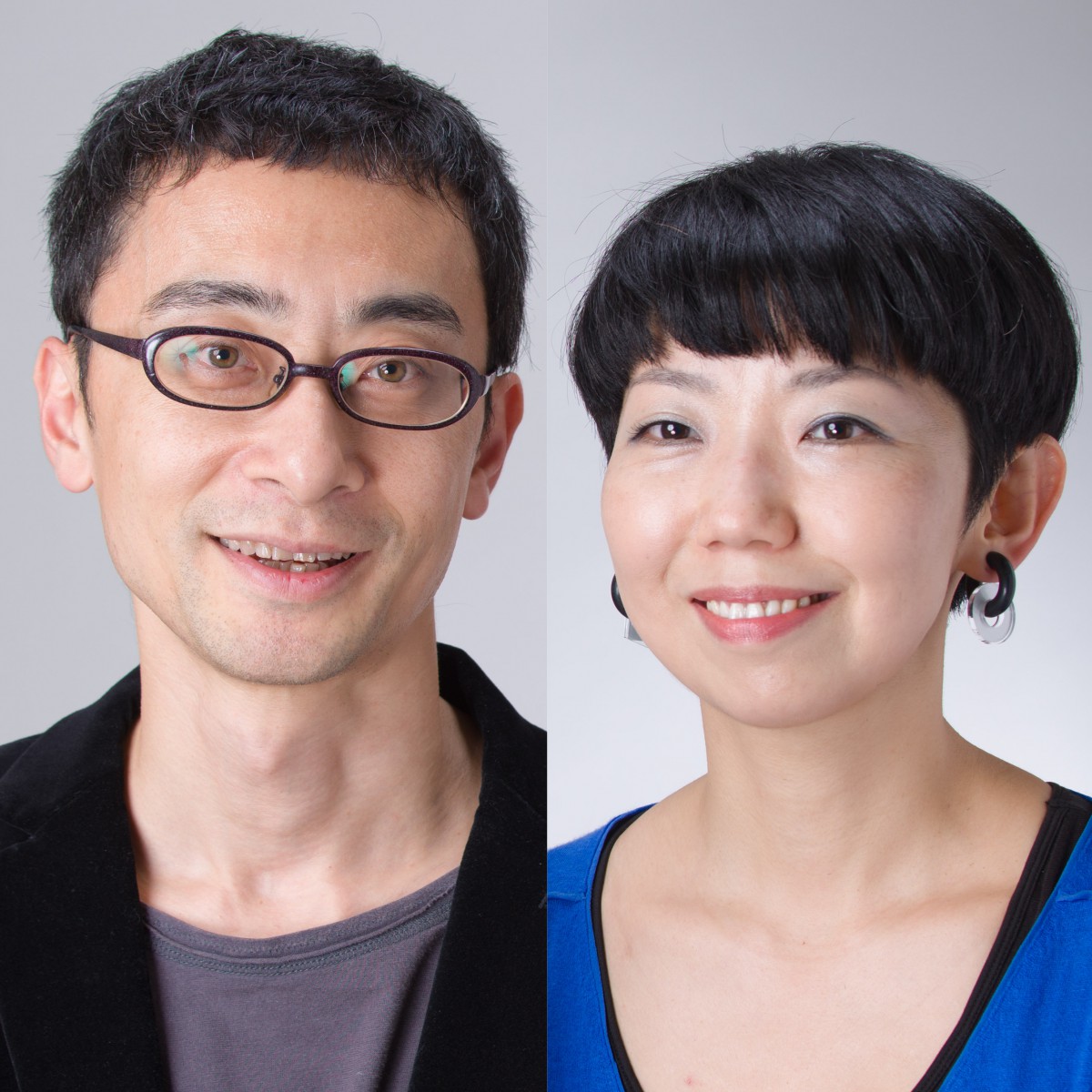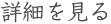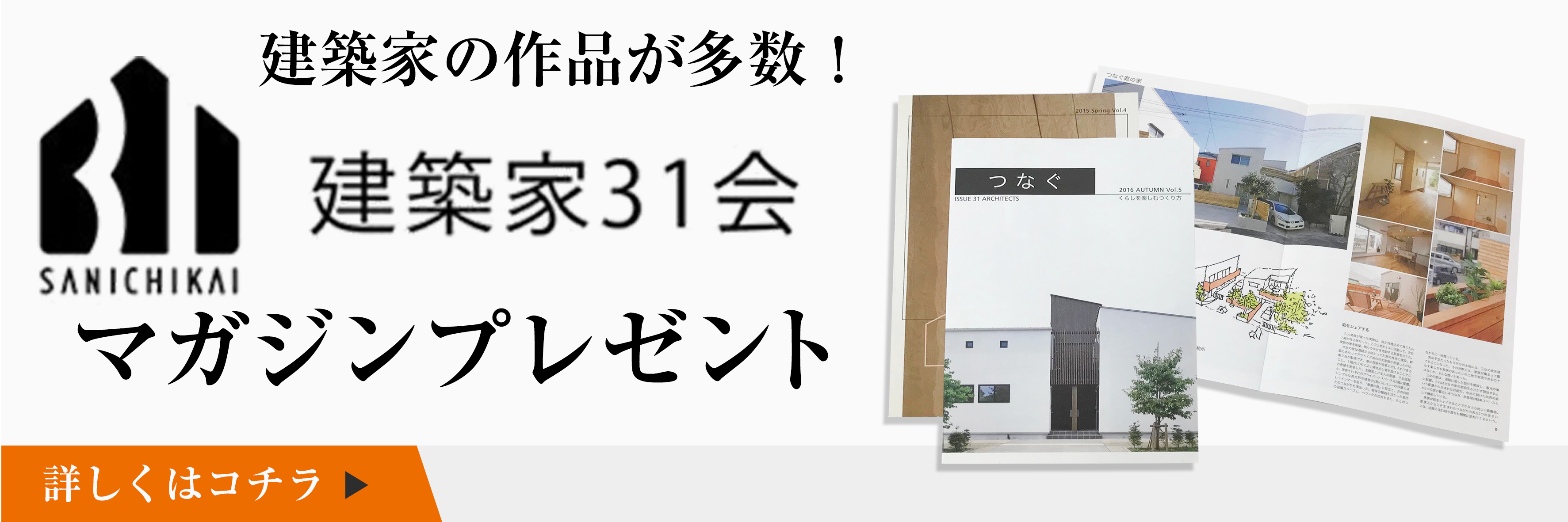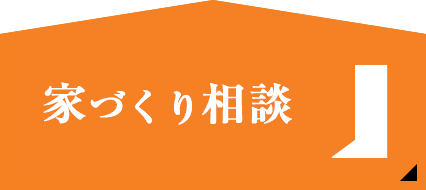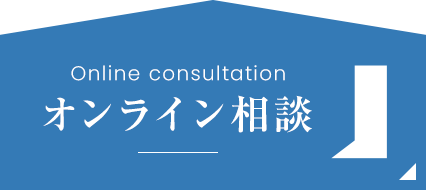平屋に中庭を設けたゆとりある庫裏の計画 @滝川淳+標由理
山梨と東京で二地域共住をしているコネクト滝川です。暑い日が続きますが、お元気にお過ごしですか。甲府盆地では夜はエアコンなしでも過ごせるのがいいところ。でも盆地ゆえに日中は風が吹かないことも多く、汗との戦いになります。桃でも食べて元気出そう、そんな毎日です。
都内に比べて土地に余裕がある甲府盆地では、家を建てるときに「平屋」という選択肢が、設計の過程で一度は選択の俎上に上がります。都内でなく地方であっても、「平屋」は土地の広さだけでなく、周辺環境や土地が広がる方位などが条件がそろえば、実現可能になります。
今回ご紹介するのは、「平屋」であり、なおかつ「中庭」をもつ住まいのご紹介。住まいと言ってもお寺の庫裏の場合の事例です。
場所は笛吹市春日居町。コネクトの山梨事務所の近くです。
浄土真宗大谷派一光山佛念寺。甲府盆地にある江戸時代から続く本堂の隣りに、住職ご家族が住む庫裏と、人が集まることができる広間を併設した住まいを計画しました。もともとあった庫裏は家族の成長に合わせて代々増築を繰り返した建物だったため、若い住職が一念発起して建て替えることに。本堂・広間・庫裏の大きく3つのゾーンは、つかず離れずの距離を保ちつつ、プライベートな空間になる庫裏はハッキリと分けることが求められました。
お寺といっても家族経営の地域に根付いた規模。お弟子さんがいるわけでもなく、住居となる庫裏部分と本堂との行き来は頻繁になるため、できれば階段はない方が良いと言われていました。また広間は、本堂で仏事を執り行った後で参加者が休憩をしたり、この暑い時期などは冷房が効いていることが重宝される空間。どうしても本堂との関係で同じ階にあったほうが良い建物になります。
すると、3つのゾーンのうち、今回計画する広間と庫裏はそれぞれ平屋であることが望ましい。土地の広がる方位としては、南北に長い敷地なので、プライベートな庫裏と広間を分けるために、あいだに中庭を設けることとしました。

写真の右側にあるボリュームが住居空間である庫裏。L型に廊下を左に進むと、広間があります。奥に見える桃の木は隣地の借景。
庫裏の側は寝室になっているので、中庭側には目線の高さの窓はつけず、大きな壁面としています。反対に庫裏につながる廊下は全面的に窓を設け、北側にあることを忘れるくらい光あふれる空間としています。
中庭は管理の手間を省く意味も含め、砂利敷きとし、庇には樋をわざと設けず、以前の住まいで使われていた瓦屋根を小端立てに並べて水当たりとしています。石臼も敷地内に転がっていたものを再利用。庭のアクセントになっています。
敷地は十分広かったのですが、3つのゾーンを平屋で計画するにはどうかな、と考えていました。どうにかうまくまとめることができました。
− 最新イベント情報 −
2月28日(土)住まいの「なかみ」構造見学会のお知らせ @小泉拓也+栗原守
どんなふうにできあがっていくのか、どうやってつくられているのか…住まいの“なかみ”とは、出来上がった時には隠れてしまうところ。見る機会の少ない工事途中を見ていただくものです。 無垢の柱や梁などの構造材、Baubioとセルロースファイバーの断熱材、通気の工夫などの“なかみ”を実際に見ていただきながら詳しく説明をします。光設計の「呼吸する住まい」の“なかみ”を見ることができるいい機会ですので、是非ご参加ください。 会場:杉並区荻窪 「スロープ玄関の小さな木の家」 ...