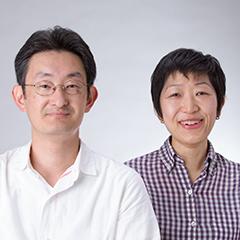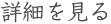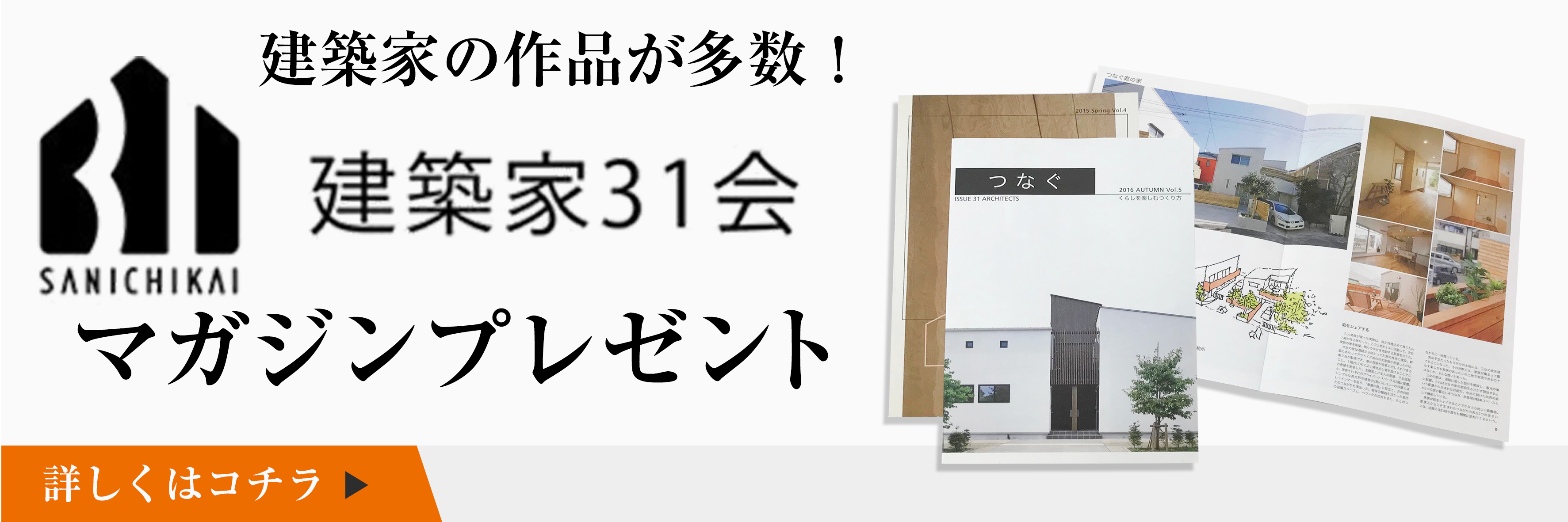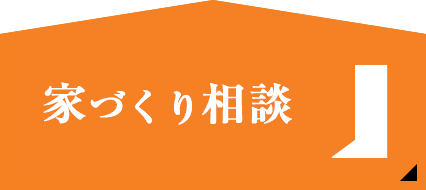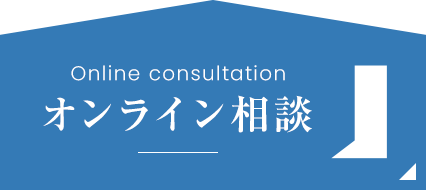音楽室のある家をつくる-5@菰田真志+菰田晶
今週のリレーブログ担当の菰田(こもだ)建築設計事務所の菰田真志です。
昨日に引き続き音楽室に関して書こうと思います。
今日は使用する室内仕上材/吸音・反射・拡散の調整についてです。
前回のブログでは部屋形状での音の調整のことを書きましたが、実際には部屋の中は仕上材があります。使っている仕上材によって音を吸収したり反射したりといった特性をそれぞれ持っています。その材料をどこに使うのかということによっても音の聞こえ方が違ってきます。
材料の種類は大きく分けると、反射(固く音を跳ね返す材料)、吸音(柔らかく音を吸収する材料)、拡散(音を乱反射させる材料の使い方)があり、これらを適所に配置することで部屋の音を作ってゆきます。
基本としては、音源のある方を前、聴者がいるほうを後ろとすると、前面は音を反射させる材料、かつ平らな面ではなく拡散させるような材料がよいとされています。音源から見て両側面も反射。後ろの面は吸音です。天井は反射。床も反射ですが客席部分などで足音対策や調整のために吸音にすることもあります。
ただ、部屋形状によっては側面にも拡散させる材料や反射板・拡散板を設置したり、後ろの面が完全に吸音だと気持ちが悪いので、吸音面の前にスリットなどで拡散の部分をつくってやったりもします。
部屋の中で出入口などがあってトンネル状になった場所などがあると、そこでの音の反響が気になることもあるので、吸音の材料を使ったり、遮音扉からの反射音が気になる場合には、扉の表面に吸音パネルをつけたりと、全体のバランスを取りながら材料を決めてゆきます。
基本は左右対象がよいのですが、なかなかそうもゆかないですから、できるだけ左右対象を意識して計画してゆきます。
大きな音楽ホールなどでは、客席がどういった材料(反射・吸音)で出来ているのか、観客(吸音!)が入った場合にどうなるのかといったことも検討しています。
客席の他にも、窓のあるなしもはっきり聞こえる要素になります。特にガラス面ははっきりとガラスからの反射音がわかりますので、どこにどの程度の大きさをあけるのかは聞こえ方に影響が大きいので注意が必要です。大きな開口を開ける場合には対策も必要になります。考え方としては「反射面に」「左右対象に」「小さい窓をばらして」つけたほうが影響は小さくなります。計画上可能であればそういった対処ができるといいと思います。
使う材料によって意匠的にも雰囲気が違ってきますので、求める音と雰囲気を考えつつ材料選びをしてゆきます・・・が、これで終わりではなく、使った材料の性能と部屋の大きさ(体積・表面積)によって残響時間が決まりますので、残響時間の計算をしながら調整をしてゆくことになります。
この残響時間の話は次回にしたいとおもいます。
よろしくおねがいいたします。
(有)菰田建築設計事務所 菰田真志
http://www.archi-komo.co.jp/
− 最新イベント情報 −
2月28日(土)住まいの「なかみ」構造見学会のお知らせ @小泉拓也+栗原守
どんなふうにできあがっていくのか、どうやってつくられているのか…住まいの“なかみ”とは、出来上がった時には隠れてしまうところ。見る機会の少ない工事途中を見ていただくものです。 無垢の柱や梁などの構造材、Baubioとセルロースファイバーの断熱材、通気の工夫などの“なかみ”を実際に見ていただきながら詳しく説明をします。光設計の「呼吸する住まい」の“なかみ”を見ることができるいい機会ですので、是非ご参加ください。 会場:杉並区荻窪 「スロープ玄関の小さな木の家」 ...